将棋が今、注目を集めています。それは、2016年に史上最年少 14歳2か月にて、
四段に昇段(プロ入り)した、藤井壮太二冠に注目が集まっているものと考えられます。
しかも、藤井壮太二冠は「王位」と「棋聖」の二冠保持だけでなく、八段昇段も決めました。
そして今回は、将棋棋士を引退した、「加藤一二三九段」と、現役棋士「渡辺明名人」、
二人の対談とインタビューで構成された書籍、
「天才の考え方」を、紹介します。

将棋とは、盤の上で、双方20枚づつの駒を使い、玉将(ぎょくしょう)を
捕獲した方が勝ちという勝敗の決め方です。
対談では、「加藤一二三九段」が、昭和から平成の初めまでの将棋について、
「渡辺明名人」が、平成から現在までを話題にしています。
昭和のころは、盤の上に記録に残る対局を再現させ、実際に駒を動かしながら、
作戦を練っていったそうです。その時に全く違う攻め方がひらめき、
実際の対局で発揮されることもあるそうです。
現在では、AI(人工知能)が将棋の世界にも浸透し、この局面なら、
駒の動かし方は、この方法が良いと、AIの回答が出てきます。
又、オンライン上で、全く違う相手と一局指すといったこともできます。
ただ、昭和でも平成でも、人対人の真剣勝負であることに、違いがありません。
相手がどのように出るか、どのように考えているのか、探りながら
指していかないとなりません。
将棋に限らず、前準備というものが、とても重要になってきます。
どのような戦法で来るのか、どのようにして不利な形成を逆転すべきか、
1つ指すのに、じっくり考えるのか、直感的に指してくるのか、
トーナメントの場合、勝ち上がっていくと、必然的に対局数も増えてきます。
体力の問題はどうか、など、考えたらきりがありません。
将棋は、盤上の戦い以前から、始まっている。一局終わった、次の戦いの
準備をしなければならない。棋士の休む時間が短く感じました。


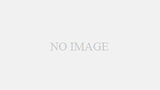
コメント